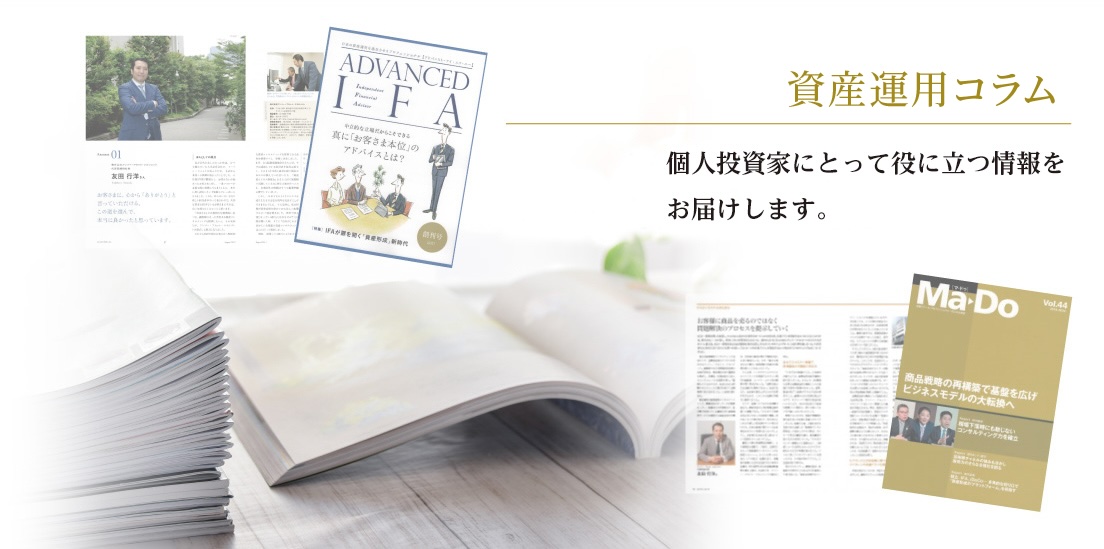
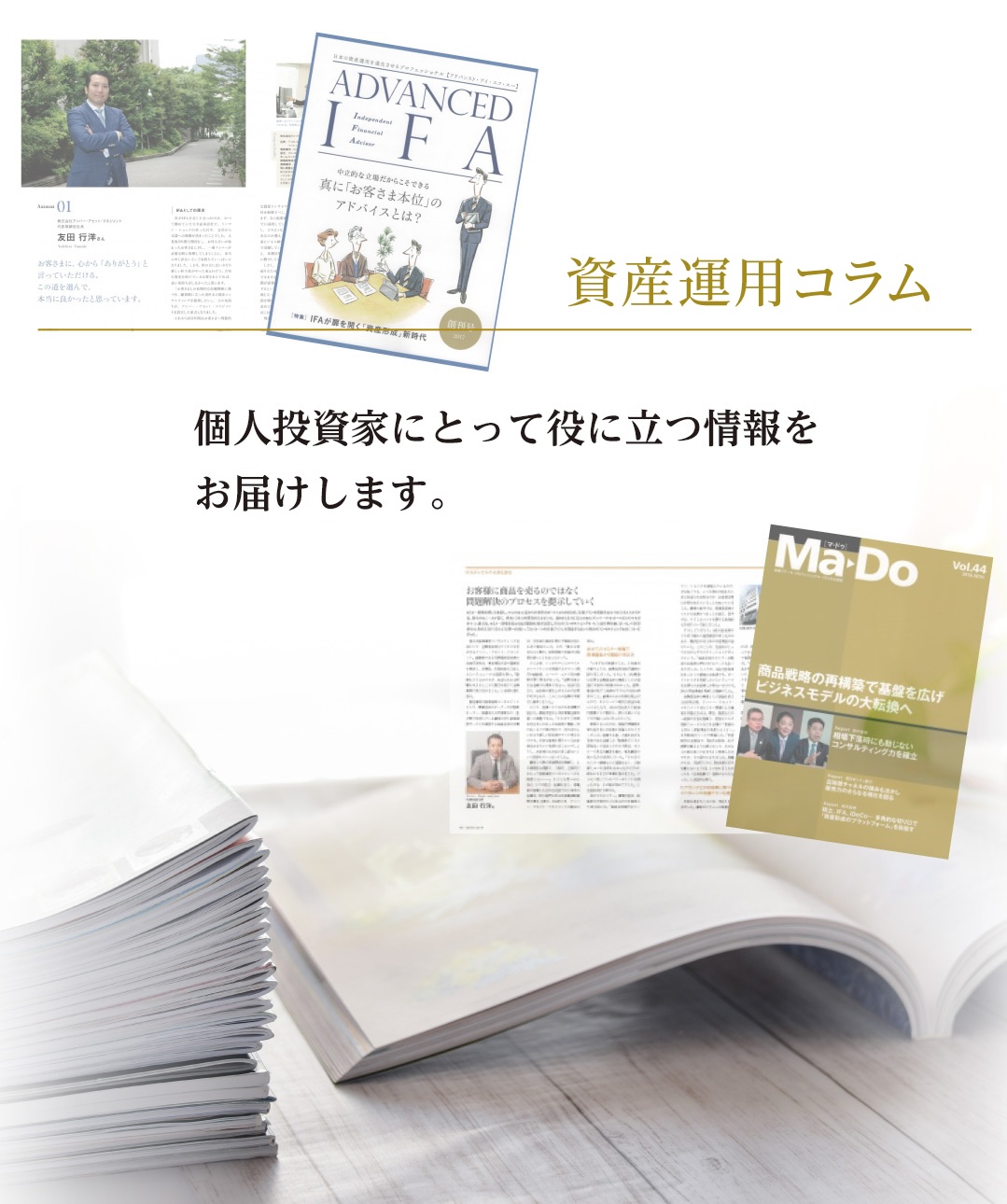
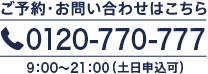
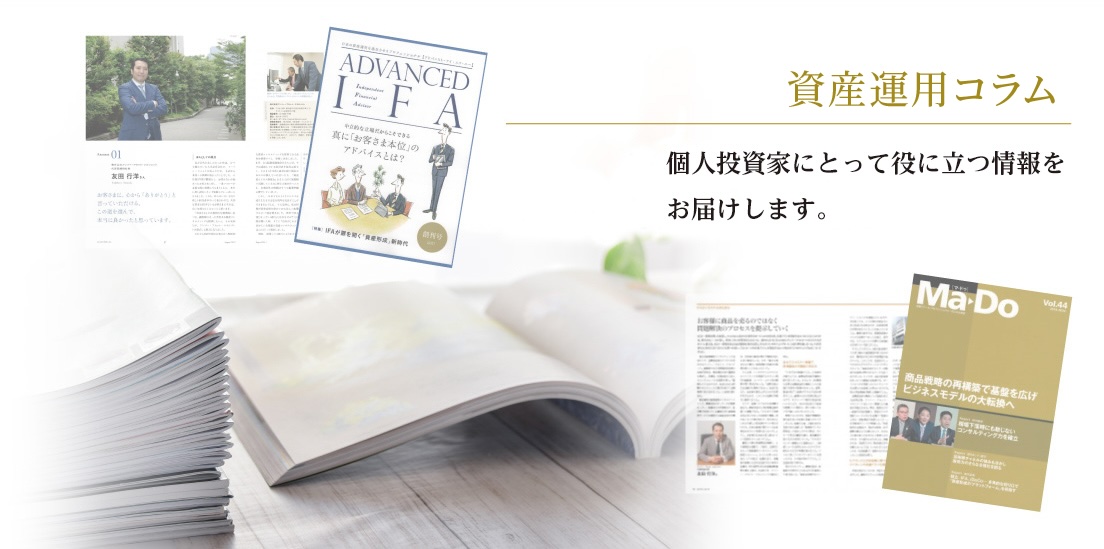
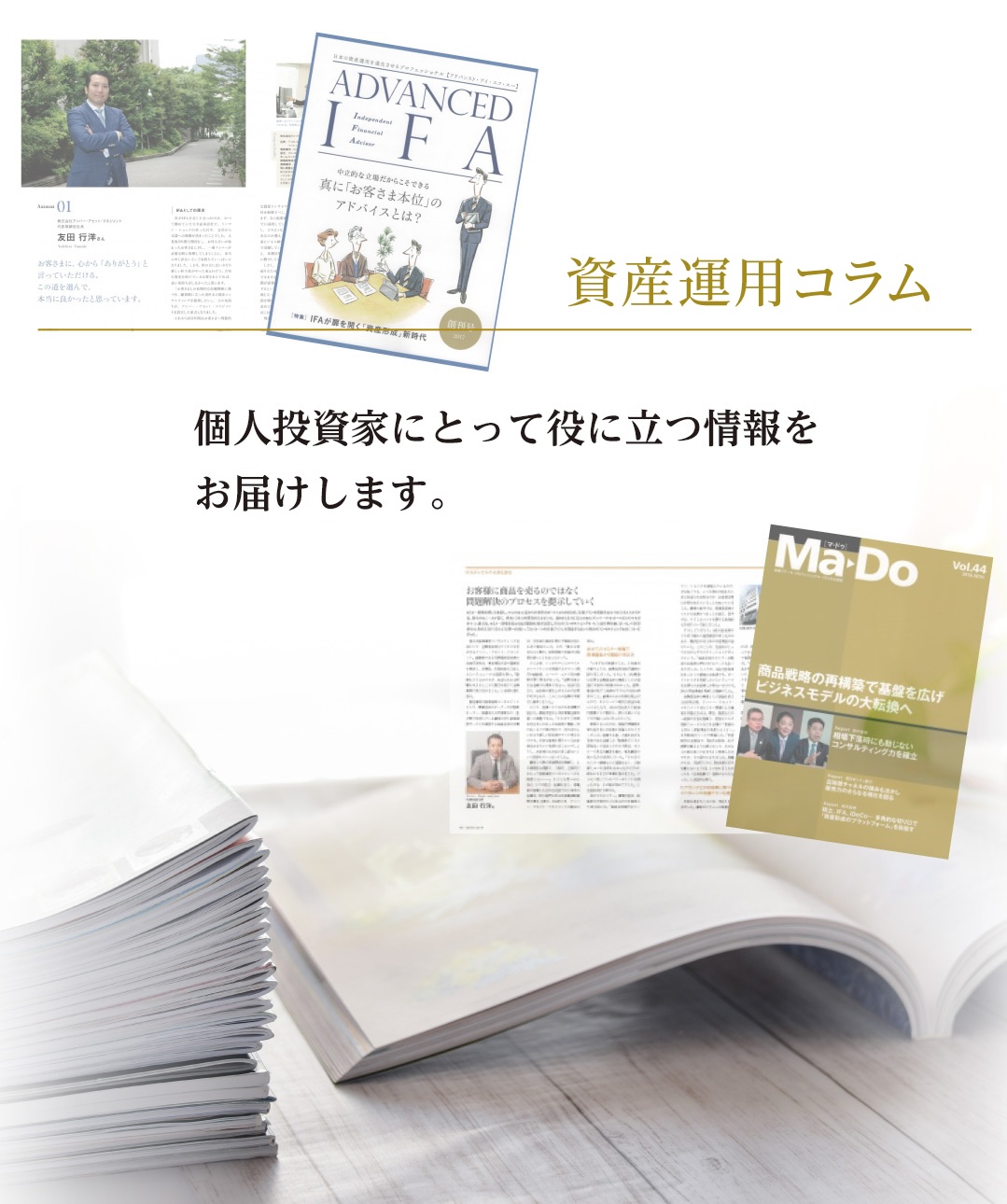


人生100年時代。老後の生活資金をどう守り、どう増やすか──これはすべてのシニア世代に共通する重要課題です。定年退職後の生活費、予想外の医療費、子や孫への支援など、お金にまつわる不安は尽きることがありません。一方で、銀行預金だけに資産を預けておく時代はすでに終わりを迎えています。
こうした背景から、今「投資アドバイザー」「資産運用アドバイザー」「資産形成アドバイザー」「投資信託アドバイザー」といった専門家の存在が改めて注目を集めています。彼らは、投資アドバイスのプロとしてお客様のライフプランに寄り添いながら、リスクとリターンのバランスを考えた運用プランを提案してくれる存在です。
本コラムでは、これらのアドバイザーが提供する価値とは何か、どのように選び、どのように付き合えば安心できる老後を実現できるのか──そんな疑問に対して丁寧に解説していきます。最終的には、信頼できるアドバイザーとの出会いを第一歩に、老後の生活の支えになる資産運用をスタートするきっかけとなることを目指します。
資産運用アドバイザーという言葉を耳にする機会は増えてきたものの、具体的にどのようなことをしてくれるのか、いまひとつピンと来ないという方も多いかもしれません。この章では、資産運用アドバイザーの基本的な役割や保有資格、具体的な業務内容について詳しく掘り下げていきます。
資産運用アドバイザーは、証券や保険といった金融商品、不動産などを使って、お客様の資産運用をサポートする専門家です。金融機関に所属するケースもありますが、近年では独立系のアドバイザーも増加傾向にあります。彼らは中立の立場から商品選定を行えるため、より顧客本位の提案が可能とされています。
一般的に、投資アドバイザーが提供するサービスには以下のようなものがあります。
●お客様の資産状況・家族構成・将来の希望などのヒアリングをもとにした商品提案
●リスク許容度を分析し、一人ひとりに適した運用ポートフォリオを提案
●投資信託、債券、株式、不動産など多様な商品を活用
●定期的な資産状況のチェックとリバランス提案
●相続や贈与など長期的な視点での助言
中でも投資信託のアドバイザーとしての役割は、近年重要度が増しています。投資信託は運用のプロが投資を代行する商品ですが、選択の仕方はその成果を左右することになります。適切な商品を選ぶには、アドバイザーの経験と知見が不可欠です。
証券、保険、不動産の仲介を行うには、それぞれ外務員資格、生命保険募集人・損害保険募集人資格、宅地建物取引士を初めとする不動産関係資格を保有し登録を受けていることが必要となります。その中でも金融商品の取り扱いのできるIFA=Independent Financial Advisor は近年その登録数が伸びています。
資産運用アドバイザーとの関係は、一度きりの契約ではなく、長期にわたって築かれる「パートナーシップ」です。特にリタイア世代にとって、将来の見通しや家族構成、健康状態などは変化しやすいため、常に変化に対応した運用戦略が求められます。そのためには、アドバイザーとの間に信頼関係がなければ、提案のベースになる必要な情報も共有することができないことになります。
では、良い関係を築くにはどうすればよいのでしょうか。まずは定期的な面談や報告を通じて、現状の資産状況と運用成果を正確に共有することが大切です。優れた資産形成アドバイザーは、単に数字を説明するだけでなく、「なぜこのような動きになったのか」「今後どのような対応を取るべきか」といった背景や見通しまで、わかりやすく説明してくれます。
また、良いアドバイザーほどお客様の言葉に耳を傾けます。「最近、孫が生まれて教育費を支援したい」「介護施設の入所を検討している」など、ライフイベントの変化を共有することが、的確な資産運用アドバイスに直結します。
資産運用は数字だけで成り立つものではありません。資産運用アドバイザーとの対話の積み重ねによって満足のいく運用成果につながるのです。

資産運用アドバイザーの質は千差万別です。広告やホームページだけでは本質は見えてこないため、慎重な比較検討が求められます。以下に、アドバイザー選びで押さえるべき5つのポイントを紹介します。
ファイナンシャル・プランナー(AFP, CFP®)や外務員、投資診断士®といった資格は一定の知識を示す指標です。また、過去の相談件数や運用成果などの実績も参考になります。
特定の金融機関に所属しているアドバイザーは、自社の取扱商品の範囲で提案を行うことになります。独立系のアドバイザー、特に複数の金融機関と委託業務契約を締結しているIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)には、中立の立場から提携している金融商品取引業者の商品の中から複数の選択肢を提案してもらうことも可能です。
専門用語を使わず、わかりやすく丁寧に説明できるか。こちらの話をきちんと聞き、理解しようとしてくれる姿勢があるかは非常に重要です。
アドバイザーへの報酬が「相談料」「成果報酬」「販売手数料」など、どのように設定されているかは必ず確認しましょう。利益相反が生じない構造であることが望ましいです。
年1回だけの面談ではなく、必要に応じて迅速に連絡が取れるかどうか。定期的なレビューやライフイベントに応じた戦略変更を提案してくれる体制があるかも重要です。
良いアドバイザーとは「積極的に商品を提案する人」ではなく、「依頼人の話を聞いて、状況に適した商品を提案する人」です。数字の実績とともに、人としての相性も重視しましょう。
ここでは、特にシニア層にとって重要性の高い「NISA」「信託」「相続」という3つのテーマにおける資産運用アドバイザーの活用法について解説していきます。いずれも単なる金融商品の知識だけでは対応しきれない部分もあり、アドバイザーの力を借りて取り組むことをおすすめします。
2024年から新しいNISAがスタートし、非課税投資枠が拡充されたことで、シニア世代にとっても魅力的な資産形成手段となりました。運用益が非課税になるNISAは、特に退職後の限られた資産を有効活用するための強力な制度です。
しかし、NISAには年間投資枠と非課税保有限度額・投資対象商品のルールがあり、適切な使い方をするにはアドバイザーに意見を聞くことが効果的です。特に「つみたて投資枠」と「成長投資枠」のどちらをどう活用すべきか、また年齢に応じたリスク管理をどう行うかなど、個別の戦略立案が求められます。
家族信託や遺言信託といった制度は、高齢者の財産を守るうえで重要な仕組みです。たとえば、判断能力が低下した後も希望通りの資産管理を実現する、あるいは子や孫への遺贈をスムーズに進めるために信託が利用されます。
このような制度は非常に専門性が高く、法律や税務の知識も必要です。ここで活躍するのが、信託の知見を持った資産運用アドバイザーです。弁護士や司法書士と連携しながら、お客様の希望に沿った信託設計をサポートしてくれます。
相続は「起きてから対処する」ものではなく、「起きる前に準備する」ものです。相続税の節税対策、遺産分割の円滑化、生前贈与の活用など、アドバイザーの助言次第で家族間のトラブルを防ぎ、資産を次世代へスムーズに継承できます。
また、資産運用アドバイザーであれば、保有中の投資信託や証券口座がどのように相続されるか、受け継ぐ際にどんな手続きが必要かまで細かく説明してくれます。
これらのテーマは、専門家であっても分野ごとの経験や連携が必要です。総合的な視野を持ったアドバイザーとともに取り組むことで、将来に向けた安心と信頼を築くことができるのです。
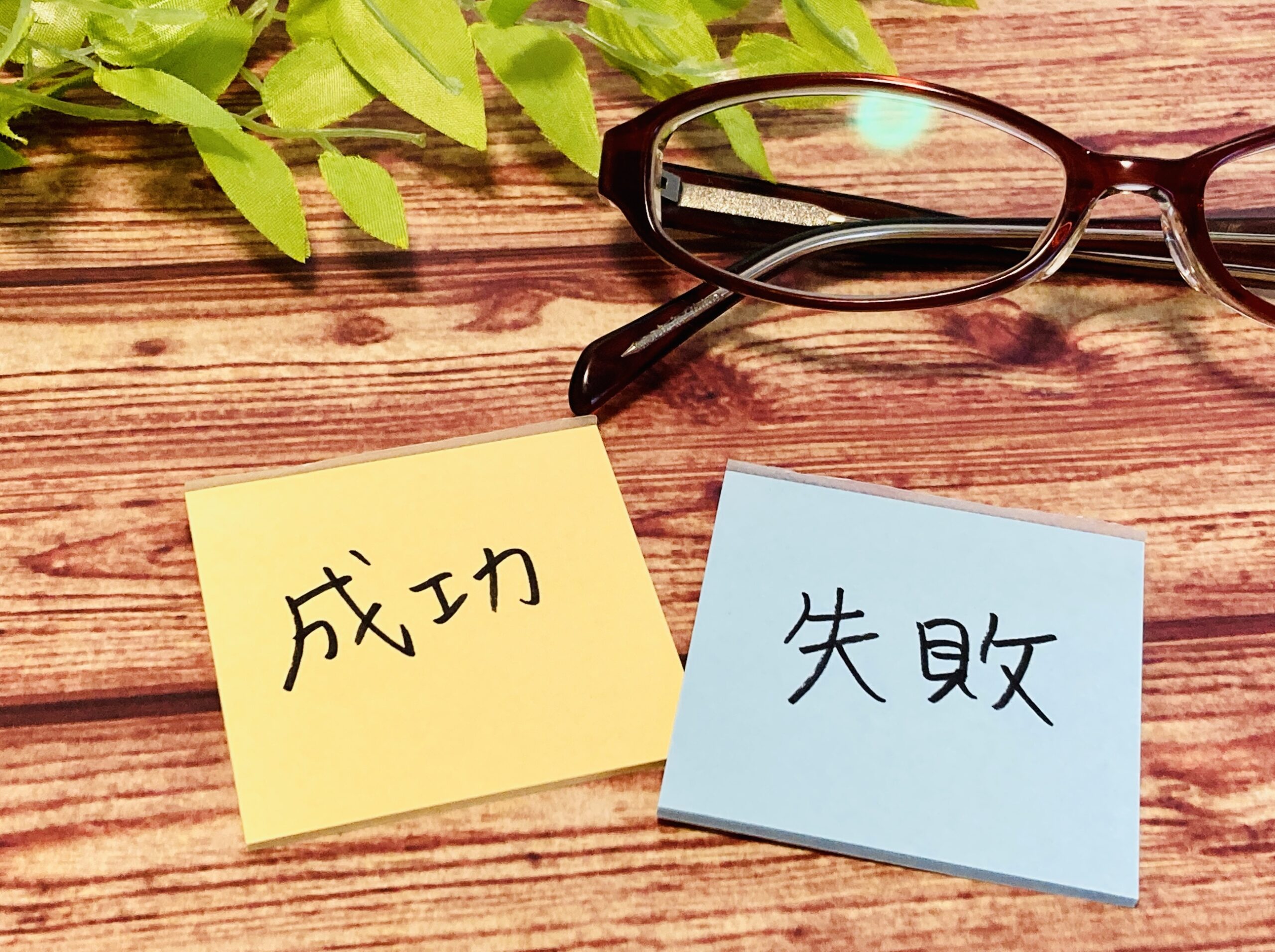
どれだけ理論が優れていても、最終的に求められるのは「実際にどうだったのか」という現実的な成果です。この章では、資産運用アドバイザーを活用した事例を紹介し、どのように成果が生まれたのか、あるいは失敗に至ったのかを振り返ることで、読者自身の選択に役立てていただける内容をまとめます。
会社員を定年退職した夫と専業主婦の妻。合計5,000万円の資産を元手に、退職金の運用方法を資産運用アドバイザーに相談。アドバイザーはライフプランを詳細にヒアリングし、年金支給までの生活費、医療・介護リスクへの備え、趣味や旅行資金などに基づいて資産を3層構造に分けて提案しました。
結果として、リスクを抑えたバランス型の投資信託と預金、一定の配当が得られる個別株を組み合わせることで、平均年利2.5%の安定した運用が実現。リタイア後10年間にわたって資産を減らすことなく生活費を補うことができ、精神的な安心感も大きかったといいます。
子どもが遠方に暮らす80代女性が、認知機能の低下を自覚し始め、家族信託の利用を検討。アドバイザーの紹介で信託設計に強い司法書士と連携し、家族信託契約を作成。信託口座で管理される資金は、将来の介護施設費や医療費にあてられるよう設計され、運用もロボアドバイザーを利用して非課税のNISA口座内で行われました。
この結果、ご本人は安心して生活でき、子どもたちも資金の流れを透明に管理できることでトラブルが防止されました。信託という複雑な制度を、アドバイザーがわかりやすく橋渡ししてくれたことが成功の要因です。
事例から学べるのは、「アドバイザーの質が人生を左右する」という事実です。信頼できる人を選ぶことは、単なるサービス選びではなく、安定した未来を手にすることに直結するのです。
信頼できる資産運用アドバイザーを見つけるために最初にできること──それが「資料請求」と「無料相談」の活用です。インターネットで情報収集するだけでは、アドバイザーの人物像や提案のスタンスまで見極めることは困難です。ここでは、なぜこの2つの行動が重要なのか、そしてどう活用すべきかを詳しく説明します。
まず、資料請求は“信頼できるアドバイザー候補”を見極める最初のフィルターとなります。実績や提供サービス、報酬体系、対応可能な分野(NISA、相続、信託など)など、基本的な情報を比較しながら、自分の希望に合ったスタンスを持つアドバイザーを絞り込むことができます。
中には、ポートフォリオ例や過去の相談事例、顧客の声が載っている資料もあり、実際の対応イメージが具体的に掴める点も資料請求の大きな魅力です。また、郵送で送られてくる資料であれば家族と一緒に検討することも可能で、相談の第一歩を家族ぐるみで踏み出すきっかけにもなります。
多くのアドバイザー事務所では、初回無料相談を提供しています。ここで重要なのは、“相談=契約”ではないということ。まずは相手の人柄や説明の仕方、話の聞き方、そしてこちらのニーズへの理解力をしっかり見極めましょう。
無料相談で確認すべきポイントには次のようなものがあります。
●初回相談の時間と内容は具体的か?(30分or60分、相談テーマの明示など)
●資料を見ながら丁寧に説明してくれるか?
●取扱商品の販売が目的ではなく、顧客の立場に立った中立的な提案がなされているか?
●相続や税金など複雑な分野への対応力があるか?
このような姿勢やスタンスを見ることで、信頼できるパートナーかどうかが判断できます。無料相談は、まさに“自分の将来を託すに値する人か”を確かめる重要な機会です。
本コラムでは、「投資アドバイザー」「資産運用アドバイザー」「資産形成アドバイザー」「投資信託アドバイザー」というキーワードを中心に、老後資産の守り方・増やし方について包括的に解説してきました。
金融知識がますます専門的になる一方で、情報が氾濫し、何を信じてよいかわからない時代だからこそ、信頼できるアドバイザーの存在は不可欠です。
●どの制度(NISAや信託)をどう活用すべきか?
●どんな商品(投資信託・保険・債券)をどれくらい持つべきか?
●どのように家族に資産を引き継ぐべきか?
こうした疑問の一つ一つに、誠実に向き合い、人生に合わせた答えをくれるアドバイザーとの出会いは、あなたの老後を大きく変える可能性を持っています。そしてその第一歩は、気になるアドバイザーへの資料請求と、無料相談での対話から始まります。悩むよりも、行動する──その一歩が、未来の自分と家族に大きな利益をもたらします。
信頼できるアドバイザーの情報を手に入れ、理想の資産運用パートナーとの出会いを始めてみませんか?
アンバー・アセット・マネジメントでは、お客様にIFAを知り、気軽にご相談いただけるよう、以下のような機会をご提供しています。
「テーマ型投資信託の売り時が分からない」「資産運用の成果が出ていない」といったお悩みをお持ちでしたら、ぜひご参加をご検討ください。
解説資料を無料でお届け
これまでに9千人以上の資産運用を分析してきたからこそ分かった
「損をする本当の理由と賢い選び方」について、
分かりやすくまとめた解説資料を無料でお届けしています。
送料も無料ですので、ぜひご請求ください。


特別セミナー
毎月、全国各地で特別セミナーを開催中。
「損をする本当の理由と賢い選び方」をテーマに、
絶対に避けたい失敗事例とその対策なども多数紹介しています。
参加費は無料ですので、お気軽にご参加ください。


個別相談
一人ひとりの資産運用の状況や投資へのご希望などをお伺いし、
投資アドバイスや改善プランをご提案する無料の個別相談も実施。
WEBの予約フォームのほか、フリーダイヤルからもお申込みいただけます。
お電話は土日も対応しておりますので、ご都合のよいタイミングでお気軽にお申し付けください。


株式会社アンバー・アセット・マネジメント 金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲)第715号
本案内に記載のセミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。
各商品等にご投資いただく際には商品毎に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。
又、各商品等には価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。
各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書、お客様向け資料等をよくお読みになり内容について十分にご理解ください。
【所属金融商品取引業者等】
株式会社SBI証券
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第44号 商品先物取引業者
加入する協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会 一般社団法人日本STO協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人日本暗号資産等取引業協会
楽天証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号
加入する協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
株式会社スマートプラス
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3031号
加入する協会:日本証券業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
あかつき証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第67号
加入する協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
・弊社は所属金融商品取引業者等の代理権を有しておりません。
・弊社は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関して、お客様から金銭若しくは有価証券の預託を受けることはありません。
・所属金融商品取引業者等が二以上ある場合、お客様が行おうとする取引につき、お客様が支払う金額または手数料等が所属金融商品取引業者等により異なる場合は、商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。
・所属金融商品取引業者等が二以上ある場合は、お客様の取引の相手方となる所属金融商品取引業者等の商号または名称を商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。